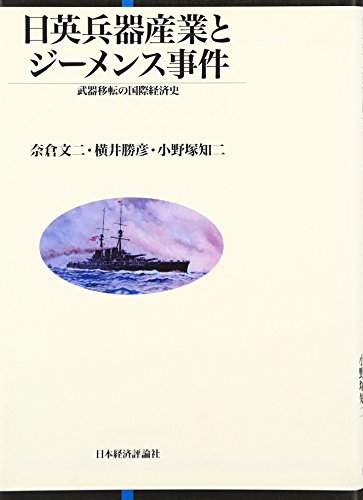第1章 軍産学複合体の前期的形成
1-1 軍産学複合体の端緒としての横須賀製鉄所
- 幕末の横須賀製鉄所設立=日本における軍産学複合体の形成の端緒
∵
- 艦船の修理・建造を目的とする工廠の設置は、幕府にとっての重要課題=軍事力の強化を解決するために設置された。
- 同所は、フランス人から造船技術を習得する組織的な技術伝習機関としての役割を持っていた。
→軍事力・産業力・技術力が一体として追求される、軍産学複合体の拠点として発足した。
- 維新後は、フランス人主導による運営から脱却し始める。
:(1)1875年にフランス人を解雇し、首長に赤丸則良を就任させる。また、造船所学科を予科と本科にわけ、本科では造船学・機械学なども教授されるようになるとともに、予科性との教育を開成学校へと委託する。=海軍の委託学生制度の嚆矢。
(2)1875年以降、造船技術の導入先をイギリスに転換させ始める。とくに、仏人ベルニー設計による「迅鯨」の不良をエルガーが解決した出来事をもって、イギリス技術依存による横須賀製鉄所の造船技術教育の体制が書くエイルした。
- 以上の動向は、技術導入のための工学教育機関の本格的整備を伴うものでもあった。
→1882年に横須賀製鉄所の校舎生徒の募集を打ち切り、海軍造船官の養成を工部大学校へ委託。
- さらに、1884年には東京大学理学部の中に海軍の川村の要請(=海軍拡張への対応策)で造船学科が設置される。→1886年、帝国大学の発足とともに、同大学の正式学科の中に組み込まれた。
- その後、1887年には工科大学に造兵学科と火薬学科の設置も実現。
☜海軍主導による造船学科の設置が、帝国大学工学部の教育・研究における軍の関与の端緒となった。
1-2 イギリスへの技術依存による日本海軍の成長
- 日本の軍産学複合体は、英国の造船技術導入による海軍拡張によってどのように成長していったか?
- 1883年に、伊藤、佐双らが欧州出張。
←国内民間海軍業社である日本共同運輸会社の船舶整備の目的を伴っていた。
※資本金の半分は政府から出資。
→政府の斡旋によって三菱と共同運輸が合併し日本郵船会社が設立(1885)。
- 当時の三菱は国内造船業において鉄・鋼の建造が技術的に不可能であった。
→海軍が共同運輸会社の汽船購入を通じての技術導入と、三菱との合併の積極的賛成[1]とによって、国内の民間海運業と造船業との育成による潜在的海軍力の強化を推進した。
→英国の建造技術に依存した鋼鉄艦の整備を主体とする海軍拡張の方針が定着。それを台頭していたのが、山本権兵衛。
山本の国内産業力の充実と並行した造船の国産化政策:
1-3 日本海軍の建設モデルとしてのイギリス軍産学複合体
- 同時代に、英国でも軍産学複合体の形成が進む。
:(1)軍-産の癒着;1889年にNational Defense Actが成立し、海軍工廠から民間兵器産業を頼る方針に転換。特筆すべきはアームストロング社。
→同社は、Admiralty Listに掲載されるために、日本からの受注によって実績を積もうとした。
→英国海軍のChief of Constructorのウィリアム・ホワイトが1883年に同社へ入社し軍艦設計を指導。(以降、同社が設計部長に海軍のChief of Constructorを就任させることが通例となった。)
←19C末の英国における軍艦建造の受発注を通じた海軍と民間産業との急速な結合=「軍産複合体」(マクニール)
(2)軍-学の癒着;1904年に英国海軍省にCommittee of Designが設置。グラスゴー大学教授のケルヴィンらが同委員会に参加する。
☜大陸では、軍事技術教育は大学ではなく軍学校内部で実施される傾向が強まっていたが、英国では総合大学の中で実施されている。
( ☜日本も英国も、海軍当局が造船教育における学理・実習の重視という観点から、大学における造船学科の設置を促進したという共通点。)
→さらに、日本で活躍した英国造船技術者が、グラスゴー大学などの学で活躍している(ex エルガー、ヒルハウス)。
- 上記の日本海軍は、イギリスの軍産学複合体の一環に組み込まれて成長した。
議論
・本章では、横須賀製鉄所設置を発端として日本の軍産学複合体の形成が始める様子と、それが英国の軍産学複合体の形成の一環として進んでいたことを論じている。
・横須賀製鉄所は富国強兵を背景とした造船産業の勃興を体現していただけではなく、造船技術者の教育機関の出現をも体現した軍産学複合体の拠点として出発した。導入先としてのフランス技術から英国技術への移行に伴なって、東京大学・工部大学校との「委託学生」制度の開始や、造船学科・火薬学科・造兵学科も設置なども行われ、軍と学の癒着が進行していった。
・加えて、日本郵船会社の設立によっても軍-民の結合にも拍車がかかった。それは民間の造船技術の向上を背景としたものでもあった。
・こうした動きを推し進めたのは山本権兵衛だった。彼は海軍大臣に就任し、艦政本部の設置も行うなど、政治力の強化にもつながっていった。
・同時代には、英国でも軍産学複合体が進行していた(以下の図)。さらに、アームストロングが海軍軍需を受ける実績稼ぎとして日本市場を位置付けていただけではなく、日本で造船技術を指導した学者がのちにグラスゴー大のポジションについている。こうしたから、日本は英国の軍産学複合体形成の一つの歯車として機能していた。

[1] これはどの程度の「圧力」と考えて良いのだろうか?「積極的賛成」とは?